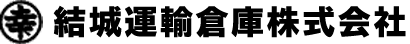社長ブログ
地名の意味
地名には意味があることが多い。その土地の歴史や形状、かつての地主の名など、様々である。ちなみに本社のある「深川」という地名は、江戸初期の人物、深川八郎右衛門が摂津の国から移住しこの地を開拓したことから、この人物の名をとって付けられたとのこと。当時は深川村と呼ばれていたが、明治に入り行政区分の編成が行われ、東京15区の一つとして深川区となり、大正昭和初期を経て戦後の1947年に隣の城東区と合併、今の江東区となった。
深川という駅名はないが地名としては残っている。警察署の名前(深川警察署)にも使われ、また当社が所属する東京都トラック協会の支部の名も深川(深川支部)。深川の名は伝統があり、愛着を感じるこの地域の地元民の象徴として、今も様々な場面で使われている。
先日、1年振りに小名浜営業所に出張した。小名浜は福島県いわき市に属し、福島県南東部に位置する。福島県は面積が広いので(全国で3番目、北海道、岩手県に次ぐ)、天気予報においては、西部(会津地区)、中部(中通り)、東部(浜通り)の3区分で伝えている。中通りは国道4号線(奥州街道)、浜通りは国道6号線(磐城街道)でもあり、この二つの国道は宮城県の岩沼で合流する。
その国道6号線の福島県玄関口に勿来(なこそ)という地名がある。国道4号線の玄関口は白河であり、「白河の関」で知られているが、勿来は白河ほど一般的に知られていない。小名浜出張時に勿来出身の社員に、勿来の由来について話を聞いた。勿来は「来ること勿(なか)れ」、つまり「来るな」という意味らしい。言い伝えでは、「敵が攻めてこないように」とか、平安時代の故事では、奥州征伐に向かった源義家がこの地を訪れた際に「来るなと言われたが来てしまった」という意味の和歌を詠んだことが由来との説もあるらしい。関所の名にふさわしく、「こちらとあちらは違う」という強い意志を反映しているんだと、話を聞いていて感じた。
今年に入って衝撃的な事故の一つ、埼玉県八潮市での道路陥没とトラック墜落のニュース。トラック業界に身を置くものとして胸がつまった。地名の話に戻すが、この「八潮」という地域は、「潮」が示す通りこの地区はかつて海だったらしい(6000年程前)。奥東京湾という遠浅の海で、その後土地の隆起や河川が運んできた土の堆積で陸地となった。つまり相対的に地盤が弱い地域のようだ(ちなみに本社のある江東区も江戸時代まではほぼ海だった)。今回の陥没も、その関連性が指摘されている。
海だけでなく、元々田んぼだった、河だった、池だった、沼だったというところの地名には、文字通り「田」「河」「池」「沼」など水を連想させる字が含まれることが多いらしい。そういえば江東区の「江」も、海などの一部が陸地に入りこんだところを指す(入り江)。
八潮の件で、地名の意味に関心を持っていたところ、小名浜での社員とのふとした会話で、さらにその関心を深堀りできた。